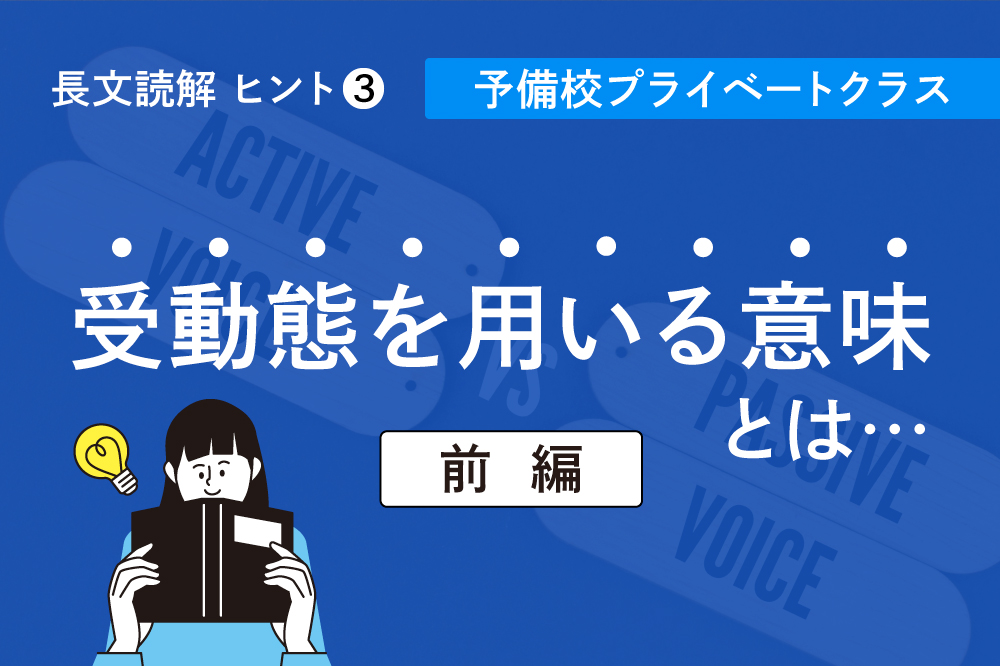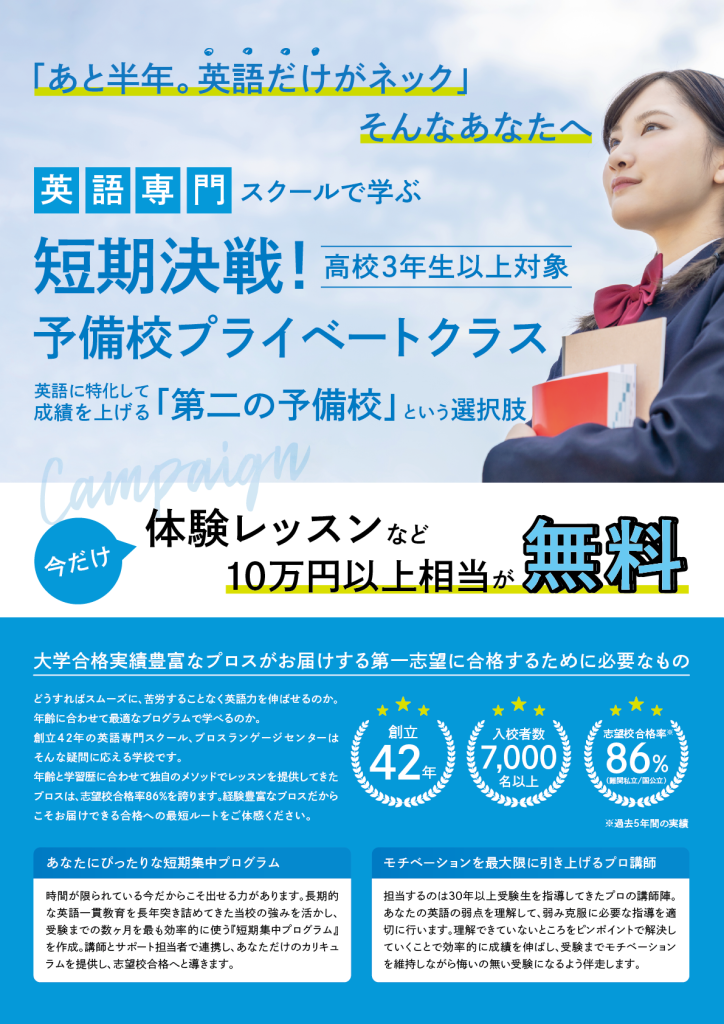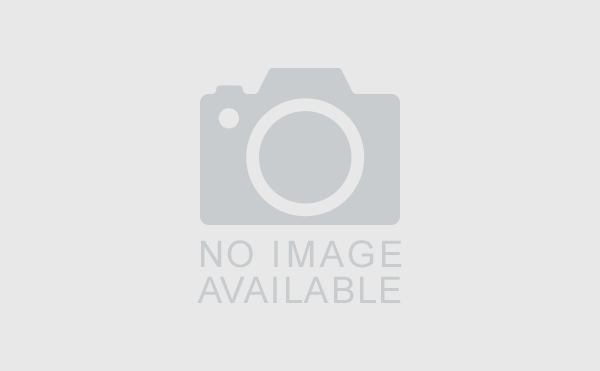【長文読解ヒント③】受動態を用いる意味とは…《前編》
今年度より開講した予備校プライベートクラス。
このブログを通して、メイン講師の安本先生に英語を伸ばしたい受験生の多くが抱えている悩みを中心に色々と質問し、現状打破のヒントを伝授してもらいます。ぜひ参考にしてみてください!
今回の質問はこちら!
Q. 英語ってやたら受動態が多くないですか?
A.その通りです。英語は受動態(「受け身」と言わないで!!)が多用される言語です(主観ですが)。日本語の「~れる、られる」が英語の受動態にそのまま対応するわけではありません。「〜れる、られる」から脱却し、その理由を2つ知るだけでも長文読解のヒントになります。
次の例文を見て下さい。
Electric computer memory is classified into ROM and RAM. ROM stands for “read only” memory. More strictly, it is “written once, read many time” memory. The pattern of 0’s and 1’s is “burned” into it once and for all upon manufacture. It then remains unchanged throughout the life of the memory, and the information can be read any number of times. Other electric memory, called RAM, can be “written to” as well as read. What the letters RAM actually stand for is misleading, so I won’t mention it. The point about RAM is that
1行に1つは受動態がありますね。1行目のclassifyは元々classify A into Bで「AをBに分類する」という使い方をします。A(述語動詞classifyの目的語)が主語の位置に移動したため、述語動詞を受動形(be動詞+過去分詞)に変えています。なんでそんなことするんでしょうね?能動態のままでいいやん!と思いますか?そうですね。能動態でいいっすよね。しかしながら作者は受動態を選択したわけですが、これにはちゃんと理由があるのです。一般的に主語と呼ばれている名詞句のことを動作主と言います。
たとえば、Tom classifies this system into three domains.「トムはこのシステムを3つの領域に分類する」の場合、このシステムを3つの領域に分類するのはTomの役割であって、他の人はしない、あるいはする必要がない、という内容を含意します。本文1行目の場合、コンピュータのメモリをROMとRAMに分類するのは一体誰なのか?という点についてはどうでもよく、一般論としてコンピュータのメモリはROMとRAMの2種類なのだ、という内容を伝えています。つまりは、メモリを分類する動作主を明示する必要はなく、むしろ動作主を明示すると上記の例のようにここで示されなかった人はメモリをROMとRAMに分類していないかのような印象を与えてしまいます。したがって、筆者は受動態を用いて1行目のように表現したのです。
受動態を用いる理由①:動作主を明示する必要が無い場合、あるいは動作主を明示すると意味内容がおかしくなる場合
次回『【長文読解ヒント③】受動態を用いる意味とは…《後編》』受動態を用いる理由の2つ目をご紹介します。お楽しみに!
予備校プライベートクラスは、これまでの英語学習で知識が詰め込まれて混乱した頭を整理して、長文を中心に「英語の本質」を捉える短期集中プログラムです。
大学受験の経験豊富なプロ講師があなたの弱点を理解して効率的に成績を伸ばし、納得の結果を出せるよう最後まで伴走します。
まずはお気軽に無料面談にお申込みいただき、ぜひお話をお聞かせください。

無料体験レッスン/面談 随時受付中
その他、ご質問・ご相談などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい